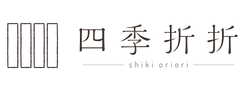栃木県益子町でシンプル過ぎず、手仕事の温もりが残る器を制作しているツキゾエハルさん。今回取り扱いさせていただくことになり、お話を伺いました!

益子焼の産地でもある栃木県益子町は、昔から日常使いの瓶や壺、水がめなどが作られてきました。大正13年に民藝運動の創設にも関わった陶芸家の濵田庄司が益子に移り住んだこともあり、県外の人たちを快く受け入れる土地柄でもあります。今ではさまざまな作風の個人作家さんがこの地に移り住んでいます。大きな窯元は少なく、3人以下の工房が約85%以上も占めるそうです。今回お取り扱いするツキゾエさんもそんな作り手さんのお一人です。
「ながく関西に暮らして居ましたが益子に来てとても暮らしやすく、
ツキゾエさんの陶芸との出会い。それは美術高校に進学するときに、第二希望としてた選んでいた陶芸科で学んだことがきっかけだそうです。(ちなみに第一希望は油絵でだったそうです。)いつも土を触っているうちに、だんだんとしっくりときて、今も自然と続けていると仰います。
制作するときに大切になさっていることは、シンプル過ぎず、手づくりの温もりがあるモノ。
「私の記憶の中に残っているうつわがいくつかあって。すべてシンプルで何気ないけれど、ちょっぴり雰囲気のあるものなんです。」
そのお言葉通り、ツキゾエさんの作品は穏やかさの中に存在感が感じられます。食卓の出番が多くなる、使いやすくて美味しそうに見えるような、そんな作品を目指して日々作陶されています。
さて、今回のお取り扱い作品のご紹介です!
口縁部に補強も兼ねて鉄釉をあしらった「皮鯨(かわくじら)」という装飾技法。焼成すると黒く発色し、その色が鯨の皮身に似ていることから皮鯨と呼ばれています。縁の滲みが趣き深い表情を作りだしていて素敵です。


オーバル皿や角皿のしのぎの器は、まるで編み物の編み目のようなコロンとした小さな玉模様を施しています。土をいっちんのようにスポイトでつけて表現しているそうです。手仕事ならではの自然な歪みやたわみ、

コハク釉は落ち着きのある飴色。どんなお料理も美味しそうに見せてくれそうです。以前はご実家の薪ストーブの灰を使っていたそうですが、現在はご友人宅の薪ストーブの灰を分けてもらい、水簸(すいひ)してアク抜きし、釉薬を作っています。

土は美濃磁器土のブレンドを使用。半磁器なので基本的に目止めは必要ありませんが、


◆ツキゾエさんのおススメの目止め方法◆
お米の研ぎ汁に20-
シンプルでやさしい風合いの中、手仕事の跡のバランスがちょうど良いセンス抜群のうつわたち。何気ない日常のテーブルがぐっとお洒落に楽しくなりそうです。
ツキゾエハルさんの取り扱い作品はこちら