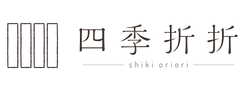うつわのお手入れ
大切なうつわを長くご利用いただくために...
日ごろ磁器を使っていた方が、陶器の特性が分からずお皿にシミが出てきてしまったりして戸惑ったりすることも。店主も初めはそうでした。でも、ほんのちょっとしたことを知っているだけで、大切なうつわを長くご愛用できます。

日ごろ磁器を使っていた方が、陶器の特性が分からずお皿にシミが出てきてしまったりして戸惑ったりすることも。店主も初めはそうでした。でも、ほんのちょっとしたことを知っているだけで、大切なうつわを長くご愛用できます。

やきものは大きく分けて”4種類”
「陶器」と「磁器」、釉薬をかけない「焼締陶器」、そして「土器」です。
代表的な焼締陶器として備前焼がこれにあたります。
陶器と磁器の違いってなんだろう?
わたしたちが日頃よく使ううつわは陶器と磁器ではないでしょうか。
その二つは見分けがつきにくいこともありますが、大きな違いはまず原料が違います。 陶器は「粘土」を用いますが、磁器は「石」を原料としています。
そのため、陶器を「土もの」、磁器を「石もの」と呼びます。
<陶器(土もの)>
〇 磁器と比べると弱い
〇 洗った後、水分が残っていると器にしみ込んだ水分がカビの原因となるので、十分乾燥してからしまう。
〇 熱しにくく冷めにくい
〇 主な産地 : 唐津・萩・美濃・益子など
< 磁器(石もの)>
〇 陶器と比べると強い
〇 洗った後、水分を拭き取ってすぐにしまってもOK
〇 熱しやすく冷めやすい
〇 主な産地 : 有田・九谷・砥部・京都など
その二つは見分けがつきにくいこともありますが、大きな違いはまず原料が違います。 陶器は「粘土」を用いますが、磁器は「石」を原料としています。
そのため、陶器を「土もの」、磁器を「石もの」と呼びます。
<陶器(土もの)>
〇 磁器と比べると弱い
〇 洗った後、水分が残っていると器にしみ込んだ水分がカビの原因となるので、十分乾燥してからしまう。
〇 熱しにくく冷めにくい
〇 主な産地 : 唐津・萩・美濃・益子など
< 磁器(石もの)>
〇 陶器と比べると強い
〇 洗った後、水分を拭き取ってすぐにしまってもOK
〇 熱しやすく冷めやすい
〇 主な産地 : 有田・九谷・砥部・京都など
使用する前に
「陶器」は無数の小さな穴が開いているため吸水性があります。その穴に少しづつ食べ物や飲み物が染み込み色合いや風合いが変わっていくことを''経年変化''と呼び、古来から味わい深い表情として愛でる文化が日本にはあります。そういった経年変化を楽しんでいただけるのも陶器の魅力のひとつになっていますが、変化をゆっくりと楽しみたい方はご使用前に陶器の穴を少し埋める「目止め」を行うことをお勧めいたします。目止めを行うことで経年変化はゆるやかになります。
<目止めの仕方>
1.お米の研ぎ汁で煮沸
うつわ全体が浸かるぐらい研ぎ汁に浸して、15-20分程度弱火で煮沸してください。(※沸騰しないようご注意ください。)研ぎ汁がない場合、代用としてごはん、もしくは小麦粉か片栗粉を大さじ1-2杯入れても目止めできます。
2.冷めるまで待つ
煮沸が終わった後、鍋の研ぎ汁が冷めるまでそのままの状態にしておいてください。
3.水で濯いでから乾燥
鍋の研ぎ汁が冷めたあと、ざっと水洗いをし、布巾で水気を拭いて十分に乾燥させたら目止め完了です。
◎ 目止め作業の時間がなかなか取れない場合
研ぎ汁や水にしばらく浸け置き(1~2時間)をするだけでも効果はございます。
窯元さんによっては、とぎ汁を使うと乾燥が不十分になりやすい為、あまりおすすめしないこともございます。また、すでに出荷前に目止め処理をしている場合もあります。窯元さんや作家さんの作品ごとのおすすめの方法を記載しておりますので、各商品ページをご参照ください。
なお、「磁器」は、凸凹が少なく、水をほとんど通さないため、基本的に「目止め」をする必要はございません。
お手入れ方法
<毎回ご使用前に>
陶器や貫入のうつわは吸水性があるため、汁物や油が入るとシミになったりします。それもだんだんとなじんではきますが、 油ものや色の濃いお料理を盛り付ける前に水さっとくぐらせるだけでも染み込みを防いでくれます 。ほんのひと手間ですが、経年変化をゆるやかにすることができます。
<洗い方・乾かし方>
使った後は残り物などをのせたままにせず、なるべく早めに洗うことをお勧めします。また洗い桶で洗うとお皿同士がぶつかって欠けやすくなりますので注意が必要です。特に粉引などの化粧土をかけたやきものは少し丁寧に。色絵や金彩の模様のあるうつわは強くこすると絵がはがれてしまうことがあります。スポンジなどで優しく洗ってあげてください。乾かす時もタオルやドライシートの上などに置き、重ねないように乾かします。いろいろな水切りマットもありますので、スペースや使い勝手などでお選びいただくとよいかと思います。
作家さんたちにオススメのお手入れ方法や気を付ける点などをお聞きすると、「しまう前に良く乾燥させてからしまうようにしてください。」と教えていただくことが多くあります。''きちんと乾かす''ことを意識されると、いつまでも清潔に長くご利用いただけます。
<収納の仕方>
しまう時には、陶器と磁器を重ねないように、形がそろったもの同士でしまってあげましょう。また、器の間にキッチンペーパーや和紙などを挟んで重ねると傷がつくのを防ぎますのでお勧めです。
<電子レンジ・食洗器の使用>
磁器は両方ご利用になっても大丈夫です。しかし、ピカピカと光った金彩の模様やデリケートな装飾があるものなどは電子レンジは使用不可です。
陶器(土もの)は強度が弱く水分を含むと熱がこもりやすいので「使用可」とかかれていても電子レンジと食洗器はおススメしません。繰り返し使うことで弱くなっていくのである日突然ヒビが入ったり、割れてしまったりします。使いたい場合は、なるべく短時間での利用のみで、冷蔵庫から出してすぐレンジをかけたりしないようになど、少し気を付けてご利用ください。
【お皿のあれこれ】 知ってるとちょっと''うつわツウ''に思われそう!
毎日使っているんだけど意外に知らない器のこと。ちょっと知っていると自分の欲しい焼き物のことが分かってきてスムーズにお買い物出来て便利です。
【うつわの各名称】
1. 口縁(こうえん)・口造り(くちづくり)・口辺(くちべり)
人の口が触る部分です。
「リムプレート・リム皿」の「リム」はこのふちの部分です。
ちなみにリム(rim)は自動車などの車輪の外枠の部分のこと。
口当たりとともに、デザイン的にも大きな影響を受ける部分です。
2. 見込み(みこみ)
うつわの内側のことです。
「見込みが深い鉢」などのようにお皿の深さを表すこともありますが、内側の中央側面部分を示すこともあります。
3. 胴(どう)
うつわの胴体。お茶碗などは絵柄が施されることが多い場所です。
4. 高台脇(こうだいわき)
高台外側の周辺です。
5. 高台(こうだい)
うつわの側面でテーブルにつく部分。
6. 腰(こし)
胴の下部分から高台脇までの個所です。

【うつわの大きさや使い方】
和食器は直径を寸または号で表記します。1寸(号)は3.3cm。約3cmだとすると5寸皿は大体直径15cmのお皿です。 尚、漢字の「寸」は右手の形に指一本を加えた象形文字で、当初の寸は親指の幅を指す身体尺であったようです。 そういえば「寸」の文字は上から親指を見た時のように見えます。なお、1尺は約30.3cmで人の指先から肘までの長さとなり、一寸はその1/10になります。
豆皿 ~3寸 (直径約9cm以下)
調味料やちょっとした前菜、箸休め、おつまみなどを盛って。大皿の上にのせたり、箸置きとしてもお洒落です。ちょっとテーブルコーデを冒険したい時には豆皿から取り入れてみるのがオススメです。
小皿 4寸 (直径約 12cm以下)
お醤油や薬味皿、漬物や少なめな前菜、副菜皿としても。大皿料理の取り皿としても活躍。
中皿 5~7寸 (直径約 15cm~21cm)
副菜やケーキなら5寸。食パン一枚なら6寸。1人用の主菜のなら7寸。色々な大皿料理の取り皿(めいめい皿)としても。使い勝手の良いサイズです。
大皿 8寸 (直径約 24cm以上)
メインディッシュの盛りつけ。 8寸ならホールケーキやパスタ。ワンプレートの利用にピッタリ。9寸のお皿ならホームパーティーで大皿料理に。
※1寸=3cmで記載
以上、参考までに記載しましたが、器の使い方は自分なりに工夫してみても楽しいと思います。
陶器は少しだけ手間がかかりますが、昔から「器を育てる」というように、年月とともに味わいがでてきます。一緒に年を重ね、互いに年とともに変化をし、家族と過ごした大切な記憶の一部となる素敵なツールでもあります。ぜひ、「自分のうつわ」になっていく愉しみを味わっていただけたら嬉しいです。
しきおり店主 もな