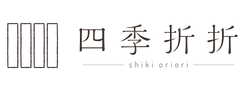茨城県で作陶されている辻中さんは、シンプルでありながら奥深い白のうつわを制作されています。当店では今回が初めてのお取り扱いとなります。制作への想いを伺いました。

辻中さんの器づくりは、形と手に持ったときの感覚のバランスを大切にしながら、重さもデザインの一部として捉えることから始まります。
「器に合った適度な重さを探しながら、形と手持ちの感覚の中で揺れ動きながら制作しています。」
どっしりとした安定感があるもの、手にしっとりと馴染むもの、器の重さは使い手にとって心地よい存在感へと変わります。重さが逆に心地よかったりする、工芸ならではの「手持ちの良さ」を追求しながら、一つひとつ丁寧に形作られています。

もともとは大学で油絵を学ばれていた辻中さん。しかし、土から生み出すものづくりに惹かれ、大学を中退。栃木県益子町で陶芸を学び、その技術と知識を礎に独自の作風を確立しました。
「どんな形にでもなる土が、どんな形にもならない時がある。それこそが器づくりの魅力であり、だからこそこの永遠に続けられる創作活動に繋がっているのだと思います。」
辻中さんのうつわの特徴のひとつが、焼成で薪を入れて燻す「炭化」という技法。これにより、赤土は深みのある黒へと変わり、釉薬はやわらかく優しい白へと表情を変えます。また、土の風合いを存分に味わえるよう高台部分の土見せを広く取るなど、細部にまでこだわりが込められています。

作陶はまず紙に何枚も線画を描くことから始まります。そこからいくつかを実際にロクロで試作し、立体としての表情を確かめながら形を探っていきます。
「しっくりこなければ、また紙とペンに戻る。頭の中にあるイメージと実際に生まれる形のすり合わせを繰り返しながら、少しずつ器の姿を見つけていきます。」
線から立体へ。何度も向き合うこの作業は、たとえ定形の皿であっても同じことだそうです。繰り返し手を動かし積み重ねるうちに、自分らしさが自然と器の中に宿るのだそうです。


益子陶器市をはじめ、さまざまな陶器市やクラフトフェアで活躍する辻中さん。美しく使い心地の良い工芸を生み出す一方で、可愛らしい猫ちゃんたちとともに、日常にそっと寄り添うような温かみのある作品づくりに励まれています。
すべてロクロで成形される辻中さんの作品は、カタチはシンプルでありながらやわらかな表情を持ち、使うほどに愛着が増していくような佇まいをしています。また、和でも洋でも、どんな料理も引き立たせてくれる魅力的な器です。何気ない日々の暮らしの中に、より一層豊かなひとときをもたらしてくれそうです。
辻中秀夫さんの取り扱い作品はこちら