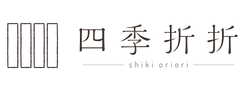磁器土の表情はこんなに豊かなんだ、、、 皐月窯さんの器を眺めていると、いろいろな感情が湧き出て心を打たれてしまいます。それは土の持つ力強さや、もちろん作り手の瑞々しい感性はもとより、手しごとならではのあたたかみ、そこに至るたくさんの過程など、いろいろなことが凝縮されてそう感じるのかもしれません。
約240年の歴史がある焼き物 砥部焼の産地でもある愛媛県砥部町で、中田太郎さん、千晴さんのご夫婦で制作をしている皐月窯さん。
それぞれ有田や砥部で学ばれたあと、太郎さんのお父さまの窯でもある中田窯で勤務。2017年に独立されます。「皐月窯」は5月に開窯されたことと、いろいろなターニングポイントに5という数字がまつわることから名付けられました。
「独立して7年経ちます。砥部の地で作陶しているのだから、ちゃんと砥部の磁器土に向き合いたいと思って製作しています。」そのお言葉どおり、皐月窯さんのオリジナリティーあふれる作品は、砥部の土をどう活かし、表現するのかという問いと真剣に向き合い、試行錯誤しながら生み出しています。白土、荒土、赤砥土、並土、この4種類の磁器土を用いて、この土だからこそ出る雰囲気を大切にし、ご夫婦2人で日々考え悩みながら作陶をされているそうです。
こちらの作品は赤砥土(あかとつち)を使用。赤砥土は白い磁器土を選別するために取り除かれた鉄分を多く含む陶石を原料にしているため、焼き上がりが黒っぽくなり、通常の磁器土とは全く違った表情に。 
今まで器づくりには使われていなかったものを、採掘屋さんがうつわ用として使えないか?と提案してくれたのがきっかけとのこと。本来使っていなかったものを活用するということで、苦労は想像に難くないと思います。何度も何度も試作を重ね、たどり着いたこの素敵な作品たち。良く生まれてきてくれた!と愛でずにはいられません。

成形は ろくろ、タタラ、型打ちを主に用いています。 くまが抱えているお魚の部分などは白化粧を削っているので、赤砥土の色が見え、落ち着きのある釉薬の色とも共鳴し絶妙な雰囲気を醸し出しています。


作品づくりには、日本の古い紋様や海外の布やタイルなどからインスパイアを受けて、そこから豊かな想像力で独自の作品が生み出されています。

磁器なので水分を吸うこともないので、目止めの必要はありません。電子レンジもご利用いただけます。ただ急冷急熱はお避けてくださいとアドバイスをいただきました。例えば、電子レンジから出してすぐに冷たいシンクに置くなどは避けてくださいね。
砥部の土の可能性を模索し、作品づくりに真摯に取り組んでいる皐月窯さん。これからもまた私たちを楽しませてくれるうつわ作りをされていくことと思います。今後の展開も今から待ち遠しいです。
皐月窯さんの取り扱い作品はこちら